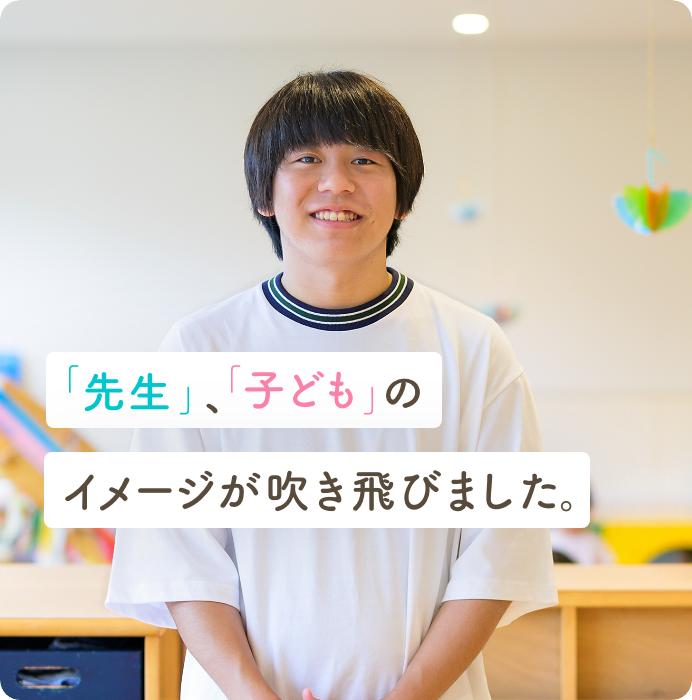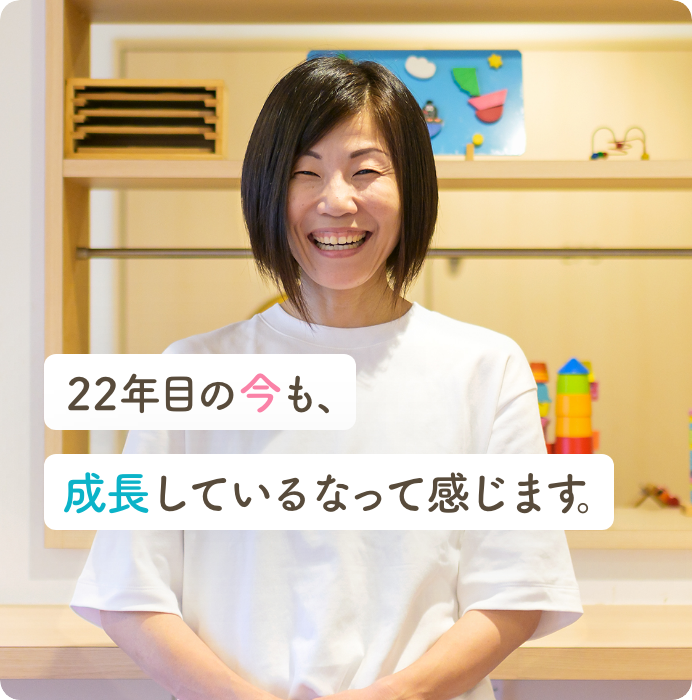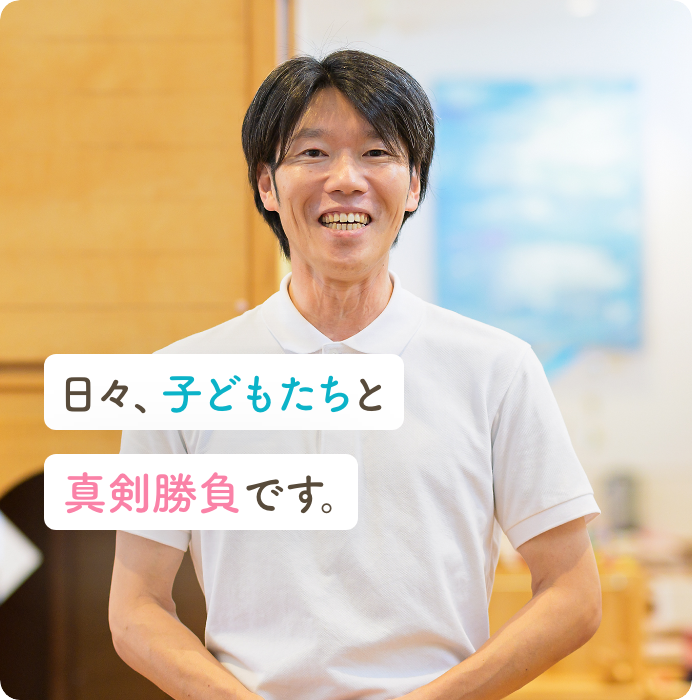採用情報
職員インタビュー
年齢もキャリアも異なる先生たちにインタビューしました。
昭代保育園のここが好き、この仕事を選んだ理由など、先生たちのリアルな声や働き方をご紹介します。
椛嶋先生
1年目(インタビュー当時)
椛嶋 稜Kabashima Ryo
- 出身大牟田市
- 四大卒業後、昭代保育園入職
子どもたちとの生活を通して見えてきたもの
入職後、先輩方のお手伝いをしながら、1カ月半の間、子どもたちと一緒に生活して、園での毎日の流れを学びました。入職前、頭の中では「先生=主導権を握っている」「先生が子どもにやらせる、させる」というイメージがあり、立派な先生にならなきゃいけないと意気込んでいましたが、ここには“先生”と“子ども”という概念がないことを、生活を通して実感しました。一人の人間同士、ともに過ごす中で、子どもが気づかない、できないところ、例えば食べ方や着替えをサポートする。ダメなものはダメと言う。あくまでも役割として子どもに寄り添う姿勢が保育者に必要なことだと気づいたんです。今、年少組をチ―フ、先輩とともに3人で担任しています。
日常の小さなことはすべて先輩方に報告してアドバイスを受け、保護者対応において敬語の使い方なども一から教えてもらいました。まだまだ、わからないことだらけなので、先輩方に頼りまくっています(笑)。
何が面白いかな? ずっとアンテナは立てたまま
まだ2カ月半ですが、毎日が楽しいです。今は先輩方が子どもたちに接する姿のマネをして学んでいます。最近は朝の活動で梅について調べました。「梅って何色だと思う?」と子どもたちに聞くと、全員が「赤」と答えたんですね。「実は緑なんだよ」と言うと子どもたちから質問の嵐(笑)。子どもたちは好奇心のかたまりですから、いつも何が面白そうなのかアンテナを立てるようにしています。子どもから見たものと、自分が見たものの違いには常に発見があり、遊びながら学んでいく保育の面白さを感じ始めたところです。
生まれてからの“6年間”に寄り添うということ
大学時代は小学校の教師志望でしたが、実習の際に考えが変わりました。保育では人格形成に最も重要な6年間に寄り添います。就学前の6歳までは、当たり前のことがまだ当たり前じゃないと感じる時期。寄り添う大人の影響力が大きいので責任重大ですが、それゆえの魅力を感じています。また嶋野先生のようなベテランの男性保育士の存在も心強く、町ぐるみで子どもを育てるのびのびとした雰囲気にも惹かれました。今は子どもたちと遊ぶ時、“自分は保育士だ”と意識していますが、無心になり全力で遊べる大人になるのが理想ですね。
古賀先生
22年目(インタビュー当時)
古賀 瞳Koga Hitomi
- 出身柳川市
- 短大を卒業後、昭代保育園入職
- 3児(大1・高2・小5)の母
自分に合わせた働き方を、親身になって考えてくれる
入職して3年後の2004年、出産・育児のために一度退職しましたが、いつかは戻りたいと考えていました。2009年に非常勤として復職し、2人の子どもを園に預けながら働いた後、2012年、第3子の出産・育児のために再び退職、その2年後の2014年に二度目の復職をし、非常勤勤務を経て、2019年に正職員となりました。私が産休育休を取得しなかったのは、育児に専念したかったからですが、当園では産休育休をとって働き続けている先生方がたくさんいます。仕事と育児の両立に不安はありましたが、それぞれのライフスタイルに合わせた働き方を、多くの先生方が親身になって考えてくれるので、安心して働くことができました。
おかげで子どもの急な発熱や入院時も付き添うことができ、今も家族行事に合わせた休日の取得なども、職員同士が普段から話し合って決めていますね。みんなが思いやりを持ってフォローし合う“お互い様精神”が根付いている職場です。
できないではなく、できるためにはどうしたらいいか
どのクラスを担任しても、子どもたちの発見や新たな発想に出合い、その思いを共有した時にやりがいを感じます。遊びや活動の中で心がけているのは、「できない」ではなく、「できるためにどうしたらいいか」を子どもたちと一緒に考え、実行すること。遊びや活動については担任の保育士に一任されています。だから私たちも常に探究心を持っておかなければなりませんが、プレッシャーはありません。ただ、自分の“ワクワクする心”を信じればいいんです。今、年長組で行っているお茶の活動は、「先生、新茶って知っとう?」という一人の疑問から始まりました。そこで家から茶葉を持ってきてもらい、匂いや形を比べてみたり、世界中のお茶について調べたり…。
子どもたちの疑問とワクワクはどこまでも広がるので、私も負けないように調べていますし、楽しいですね(笑)。対話をしながら活動していくことで、子どもたちの「考える力」や「個性」を保育者が引き出すのではなく、お互い引き出し合うことができるんです。そこには“先生と子ども”ではなく、“人間同士”のやりとりがあります。
ほかにどんなことが学べる?可能性は無限大
日々、園の理念「ともに生き、ともに育ち合う保育」を実感しています。定期的に外部講師を招いての研修をはじめ、他園や関連施設の見学、交流を通して、職員が成長できるのも当園の特長です。先日、外部の先生からアドバイスをいただきましたが、刺激になるとともに、保育者として、まだまだ成長の段階なんだなと実感しました。今後も現状に満足することなく、遊びの環境や子どもへの伝え方などを模索し、学びの可能性を追究していくつもりです。
My favoriteココがお気に入り
エントランスにある水槽の水面が床に反射し、キラキラと輝いて虹のような色になることも。「今日は虹ができとう!できてない?」と床にへばりついて離れない子どもたちの姿を見るのが大好き。
嶋野先生
23年目(インタビュー当時)
嶋野 安男Shimono Yasuo
- 出身熊本
- 短大を卒業後、昭代保育園入職
- 23年目、2児(中3と中1)の父
息子たちも今の「昭代保育園」に預けてみたかった
当園ではいち早く、一斉保育から子どもたちの自主性を育む保育へとシフトし、子どもの興味をじっくりと探究できるような環境構成を整えています。子ども主体の保育は保育者としても、一保護者としても理想でした。しかし実践面では難しいこともあります。当園では「みんなに開かれた居心地のよいところ」を教育・保育方針としていますが、一人ひとり個性があり、居心地の良さも違う。そこで今、私が挑戦しているのは「遊びに本気になる」ということ。例えば、今までは全体の様子を見ながら遊びの集団に入り、子どもたち同士をつなぐパイプ役をしていましたが、今は集団の一人になり、子どもたちと一緒になって真剣に遊んでいます。
この活動を通して、子どもたちと一対一の人間同士として、より深く付き合えるようになった気がします。また他人や個性を尊重する思いを子どもたちから感じられるようになりました。日々、試行錯誤の繰り返しですが、発見が多く楽しいですね。
先輩も後輩も男性も女性もみな同じ“保育者”
22年前、男性保育士を募集していたのは当園だけでした。憧れの保育士になったものの、当時は子どもとどう接していいかわからず、常に悩んでいましたね。そんな時、優しく接してくれたのが周りの先生方でした。当園では主任でも新人でも対等な関係です。昔から職員同士のフォローや協力体制が根付いているんです。勤務時間内に参加できるオンライン研修など、職員が現場以外に学べる機会もありますし、着実にキャリアを積める環境が整っています。キャリアとともに給料もアップするので、モチベーションを保ちながら仕事に取り組むことができます。またICTによる業務のスリム化が進んでいるので、以前と比べ、家で過ごす時間がかなり増えました。休日もしっかりとれますし、ワークライフバランスを実現することができる、働きやすい環境も当園の大きな魅力です。
子どもたちから学ぶことは、数えきれないほどある
時代に合わせた柔軟な対応も当園ならでは。「保護者1日保育体験」など新たな試みにもチャレンジしており、常に職員が教育・保育に集中できる仕組みづくりを考えています。当園では「子どもを、常に問いを持ち、探究する有能な存在」としてとらえていますが、日々感じているのは、子どもは大人が思うほど未熟ではないということ。子どもの物事に対する探究心や考える力の強さ、その発想力に驚くこともしょっちゅうあります。そんな子どもたちから学ぶことは数えきれないほど。これからも子どもたちとずっと一緒に探究し、学び合いたいと願っています。
採用についてのご質問やエントリーはお電話でもWEBからでも受け付けています。
気軽にお問い合わせください。